
今回は、相続と贈与の一体化について解説します。
・相続と贈与の一体化に関する2022年度税制改正での扱いは?
・2021年度税制改正大綱と2022年度税制大綱の違いとは?
・相続と贈与が一体化した場合、何が変わるのか?
2022年度税制改正
暦年贈与(年間110万円までの贈与は非課税)は昔からある相続税対策です。
昨年公表された「2021年度税制改正大綱」では、諸外国の制度を参考にして、今後、相続税と贈与税を一体化して課税(つまり暦年贈与は廃止ないし制限すること)することを検討する旨が記載されていました。
しかし今回の「2022年度税制改正大綱」では見送られました。
したがって、しばらくは暦年課税での対策ができることになります。
税制改正大綱(2022年度、2021年度対比)
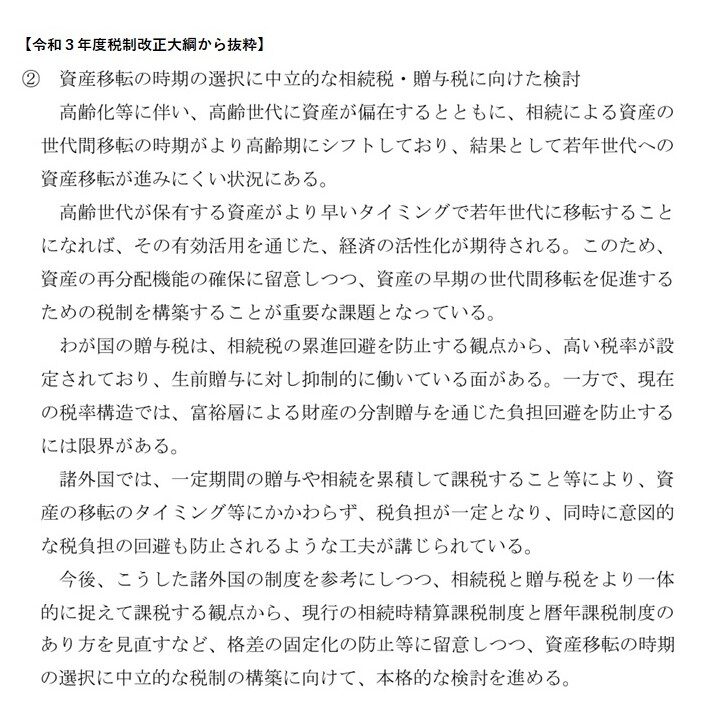
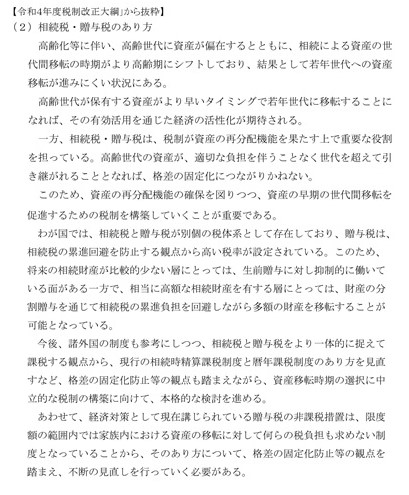
出典:自民党「2022年度税制改正大綱」相続税と贈与税の一体化とは?
相続税と贈与税の一体化とは「相続で財産を渡しても、贈与で財産を渡しても、かかる税額を同じにする」税制改正のことです。
つまり、財産を移転する際の税金は、生前、死後に関係なく同じにするということです。
今後の税制改正で検討されているのは以下の点です。
暦年贈与の廃止
現在は、年間110万円までは無税で贈与(暦年課税制度)できます。
しかし今後、この暦年課税制度が廃止され、相続時精算課税に統一される可能性があります。
【参考】ブログ「そもそも贈与税とは?」
持ち戻し期間(「相続」と「贈与」を分ける期間)の変更
現在は、
「生前贈与をしてから3年以内に亡くなった場合、相続税の計算上、3年以内に贈与した財産も加算して相続税を計算する」
というルールがあります。
今後、諸外国を参考にして、この持ち戻し期間が長くなる可能性があります。
また現行制度では、この持ち戻しルールは孫・曾孫には適用されません。
税制改正によって、今後適用される可能性があります。
まとめ
2022年度税制改正では「相続税と贈与税の一体化」について具体的に踏み込むことはありませんでした。
しかし今後、間違いなく税制改正が行われます。
中小企業経営者の方にとって、自社株評価、その他の相続財産の棚卸、相続税・贈与税のシミュレーション、遺言書作成、といった相続・事業承継対策をする良い機会だと思います。
