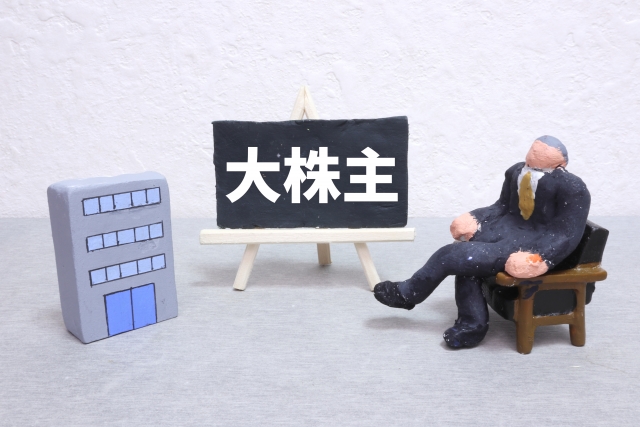会社経営にあたって、株式の議決権割合と会社支配の基準を解説します。
・株主総会の決議は、頭数の多数決ではない?
・特別決議を単独で決議できるのに必要な議決権割合は?
・株主総会は何種類ある?
このブログは、2019年8月27日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。
目次
議決権の割合と行使できる権利
株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有します。
しかし、単元株式数を定款で定めている場合、一単元の株式につき一個の議決権となります。
これを一株一議決権、一単元一議決権の原則といいます。また、相互保有株式※1や自己株式※2に議決権はありません。
経営者が所有しておくべき議決権割合は?
まとめ
事業承継や自社株式の買い取り、VC(ベンチャーキャピタル)からの出資の際に、社長としてどの程度の議決権を持てばよいのか、悩ましいところです。そのときの株価も関係しますので、事前に専門家に確認したほうが無難です。
【参考】ブログ「あなたの会社に出資したい」