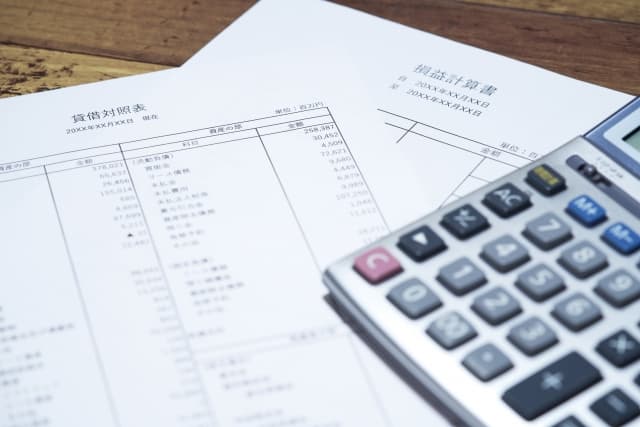今回は、「取引相場のない自社株式」を相続・贈与する際の適正な株価の決まり方について解説します。
✅ 後継者や親族、従業員…誰に渡すかで株価が変わる?
✅ 「取引相場のない株式」はどのように評価されるのか?
このブログは、2022年10月25日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。
目次
取引相場のない株式の算定方法は?
中小企業のほとんどは非上場会社です。したがって、株式に取引相場はありません。上場企業のように、需給によって、毎日株価が変動しているわけではありません。
なお、「取引相場のない株式」の算定にあたっては、会社規模、株主構成、類似業種株価、など計算の大部分が財産評価基本通達(国税庁)に定められています。
【参考】ブログ「自社株式(非上場)の株価算定方法は?」
※今回のブログでは、特定の評価の会社(清算中の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業前の会社)は扱っておりません。